命を守るために!我が社の自衛消防隊!!~学校法人阿邉学園 あざみ野こども園編~
登録日:2025年3月1日
『学校法人阿邉学園 あざみ野こども園』で消防訓練を実施しました!
このコンテンツは、「自らの職場は自らが守る」をコンセプトに、事業所における自衛消防隊の果たすべき役割をあらためて認識
し、災害発生時に有効、かつ、適切な活動ができる自衛消防隊の育成と防火管理の強化を図ります。
また、自衛消防隊の日頃の活動を紹介することで、市内の多くの事業所への防火啓発を目的としています。
事業所の紹介
■事業所名
学校法人阿邉学園 あざみ野こども園
■所在地
いわき市川部町赤坂110番地
■代表者
学校法人阿邉学園 園長 阿邉 みどり
■従業員数
23人(令和6年度)
あざみ野こども園 園長先生のインタビュー
当こども園は、1歳から5歳児までの園児が登園し、日中を過ごしています。今昔、いろいろな災害に対応するには、日頃から職員・園児の訓練が不可欠と考えております。幼児と共に行動するため、毎月火災・地震・水害の訓練をしております。来年度は、地域の小中学校・公民館さん等との連携を図る話し合いもしているところです。
《ココがPOINT!》わたしたちが独自に防火・防災に力を入れているところ!
■副園長先生のコメント
当園は、子どもたちの安全を確保するため、災害を想定した訓練を毎月欠かさず行っています。
園舎が1・2歳児クラスと3・4・5歳児クラスが渡り廊下でつながっておりますが、あらゆる災害時にいち早く安全な場所へ誘導できるよう、職員一人ひとりが避難経路や必要な行動について共通認識を持つようにしております。また、各フロアにどの位置からも避難誘導灯が目視できるよう配置され、来客があっても避難誘導できるようになっております。
大規模地震を想定した訓練では、保護者と連携を図り,引き渡し訓練を行います。訓練後の振り返りも大切であり、改善策を次に反映させています。
年2回の消火器の点検や年1回の勿来消防署員の方々の立ち会いによる通報、水消火器を使った消火の訓練も実施しております。
今回の訓練をしてみて
「自衛消防隊長」のコメント
万が一の火災を想定し、毎月訓練を行っていますが、冷静さを保ち誘導する難しさを感じます。
今回の火災を想定した訓練では、職員間の連携もよくスムーズに流れたと思います。その中で、自身の課題として、火災発生を知らせる非常ベルから園内放送までの時間短縮などがあり、習熟の大切さを改めて感じました。
今後も、子どもたちの命を守るため、安心してお子様を預けていただくため、防火管理者として防災意識をもって防火管理に努めたいと思います。
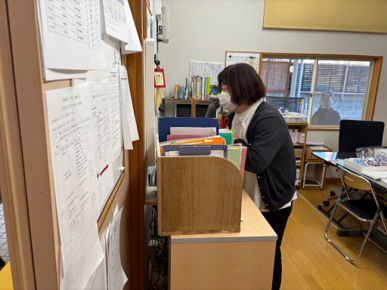
《訓練開始の全館放送》
「119通報担当」のコメント
今回は、訓練で119番通報をしました。住所や電話番号は言えましたが、通報と同時に病児のお迎えと重なり、園児の人数変動を確認するのに時間がかかり、職員数と園児数をすぐ答えることができませんでした。今現在の園児数、職員数を常に把握できるよう連携し、何時であっても即答できるよう努めたいと思います。

《通報訓練》
「避難誘導担当」のコメント
園児も不安なく、スムーズに防災頭巾を被り避難することができました。
避難する際、室内の点検(窓や入口ドア)は、園児誘導を優先すると疎かになってしまいますが、他の職員が点検をしてくれたことにより、安全に誘導することができました。今後も、連携を図りながら、子どもたちの安全を守りたいと思います。

《防災頭巾をかぶって避難準備中!》

《避難開始!》
「初期消火担当」のコメント
今回は、模擬消火を行いました。緊張感を持って取り組みましたが、考えていたようなスムーズな動きができなかったように思います。今後も、消火器の取り扱い訓練も含め、災害時にすぐ対応できるよう、習熟に努めたいと思います。

《消火器での模擬消火訓練》
消防署からのメッセージ
《訓練指導消防隊》隊長からのコメント
訓練大変お疲れ様でした。まず、訓練開始のアナウンスが流れてから防災頭巾を子供達に被せるまでの速さが素晴らしかったと思います。子供達も先生の指示を良く聞き、落ち着いて避難できていました。初期消火に関しては、出火室に設置されている消火器ではなく、より安全に取りにいける廊下の消火器を取りに向かわれていたので、火災をしっかりとイメージしながら対応できていて良かったと思います。通報訓練では、冷静な話し方と細かな質問への対応力が素晴らしかったと思います。
最後に、全体的に習熟度が高く、子供達の命を預かる責任感や真剣さが伝わってきました。我々消防職員も訓練指導の立場でありながら学ばさせて頂き感謝しております。今後も訓練継続をよろしくお願いいたします。

《消防隊隊長による講評》
《勿来消防署》予防係長からのコメント
寒空の中の訓練お疲れ様でした。定期的に様々な訓練をされているため、今回の訓練にも対応できたのだと思われます。
私が常々思うことがあるのですが、災害弱者(高齢者や乳幼児など)を屋外に避難させた後、いつまでもその場にいることもできません。二次避難として、どこにどのようにして避難させるかというのも重要になってくると思います。その時の天候状態なども考慮し、人員の把握や、いち早い行動が必要になってきます。初期消火なども重要ですが、人の命を預かる施設としては、避難誘導が最優先と私は考えております。今後の訓練においては、二次避難行動なども取り入れるとさらに良い訓練になると思います。
《勿来消防署》署長からのコメント
防火管理の目的は、いかに施設の安全を確保するかにあり、具体的には、火災を出さない(出火防止)、火災になっても延焼させない(延焼拡大防止)、火災による死傷者を出さない(死傷者発生防止)の三点となります。近年、全国的に出火件数は減少傾向にありますが、生活様式の変化等により、電気器具や配線に起因する火災が増加傾向にあり、出火防止の観点からは、火気の使用場所のみならず、施設内の電気器具等の取り扱いや維持管理に留意する必要があります。また、延焼拡大防止、死傷者発生防止は、自動火災報知設備による火災の早期発見、消防機関への適切な通報、消火器等を使用しての初期消火、園児の避難誘導、避難介助等、その多くを自衛消防組織が担うことになります。火災等の緊張を強いられる場面では訓練された行動については行動のパフォーマンスが上がるという知見があり、自衛消防組織の力を最大限に発揮するためには、施設内に設置されている消防用設備等の取り扱いに習熟するとともに、火災の発見から避難誘導に至る全ての項目について適切に活動できるよう繰り返し訓練する必要があります。施設の安全を確保するためには、以上のことが将来にわたって確実に実施できるよう心掛けて下さい。
この記事についてのお問い合わせは、勿来消防署まで
勿来消防署(担当:予防係)
電話番号:0246-63-2248
「命を守るために!我が社の自衛消防隊!!」
消防本部では、これからも「命を守るために!我が社の自衛消防隊!!」のコーナーで各事業所の特色のある消防訓練を掲載して
いきます。
ご覧になられている皆様の事業所でも「こんな訓練をしている!」などの、「訓練自慢」がありましたら、最寄りの消防署へ‼
このページに関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
電話番号: 0246-24-3941 ファクス: 0246-24-3944
